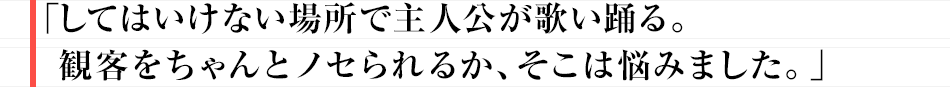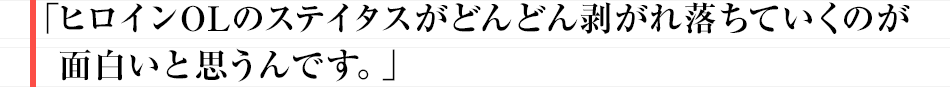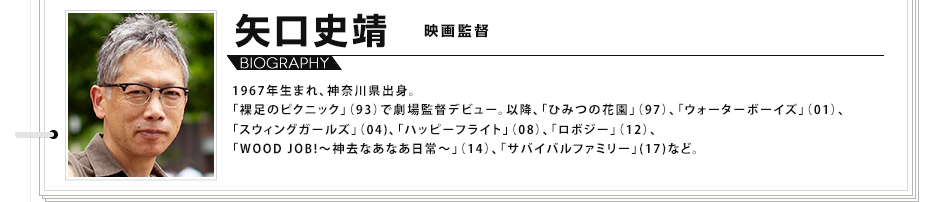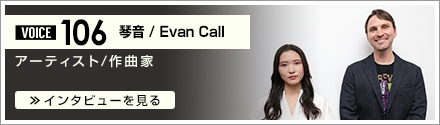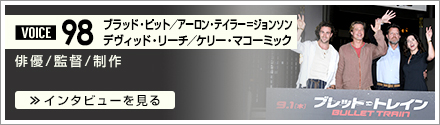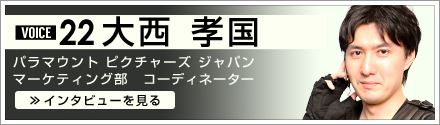―ミュージカル映画に対する苦手意識から本作のアイデアが生まれたそうですが、そもそも苦手だと自分で意識された映画について教えてください。

ミュージカルは、テレビで「ウエスト・サイド物語」を見たのが初めてでした。「お!」と新鮮な驚きがあって、それから色々観ましたし、ダンスや歌のシーンも好きは好きです。でも、やっぱり違和感も同時に覚えていて。導入が上手くなくて、“おっと、何で急に歌うんだよ”、となる作品も結構あって。人の生活空間や街中でいきなり歌い出したり踊り出したりすることに、誰もツッコまない。どうせ僕が作るのなら、歌ったり踊ったりする必然のあるミュージカルを作りつつ、その鉄則を破って“ツッコませる”ということがしたかったんです。
―必然のあるミュージカルにするための“催眠術”というアイデアが、バカバカしいだけに秀逸ですね!

しちゃいけないところで主人公がミュージカルをやらかし、すればするほどピンチになる、ということだけは決まっていて、催眠術を思いつくには少し時間がかかりました。でも思いついた瞬間、“これはイケる!”とも思いました。
―ミュージカル作品であるがゆえに、大変だったこと、勝手が違ったことはありましたか?

一番のテーマはやっぱり、現実の世界で主人公が歌い踊ることなので、ミュージカルする前と、しでかした後のリアリティをどうやって描くかに注意を払いました。何しろ本作では、ヒロインは不審者扱いされますから(笑)。その上で観客をちゃんとノセられるか、というのが最大の難点でした。
―自分でも嫌なのに、体が勝手に…という表情と動きを組み合わせて作るのは、ヒロインを演じた三吉彩花さんも相当、難しかったでしょうね。

そう思います。絶対やっちゃいけない場所なのに、音楽が聞こえると“あたし、踊っちゃうのよね”という特殊な状況なので(笑)。特にムロツヨシさんと三吉彩花さんが駅前にいて、時報の音楽が流れるシーンでは、歌を止めたり、復活させたりするという、現実と催眠状態が入れ替わる場面は、かなり悩みました。
―監督の作品は、昔から“ヒロインが受難にあう”物語が多いですが、今回は“一流企業勤めのOL”が受難に遭います。

一流企業のOLさんに決して恨みを持っていたわけではなく、学生さんだと、これだけ踊れたらクラスのヒーローですからね。ちゃんとした社会人のキラキラOLが、広いオフィス、しかも会議中に踊るという不謹慎極まりないことをすることで、たくさん身に付けたステイタスがどんどん剥がれ落ちていくのが面白い。しかも東京のど真ん中で、お金もあった彼女が、気づいたら着の身着のまま、メイクもせず、お金もなく、微妙な女の子たちと一緒に車に乗って、田んぼや畑や川しかない広い空の下を走る。でもそこで、本来の自分に気づくという風にしたかったんです。「サバイバルファミリー」では九州に行ったので、今回は逆に北に向かいました(笑)。
―では最後に、監督は催眠術を試されましたか?
何度も掛けてもらったのですが、心が汚れているからなのか、全く掛からない(笑)。楽しい催眠なら掛かりたいのに、人生損をしていると思いました。