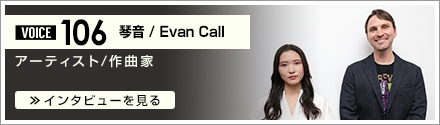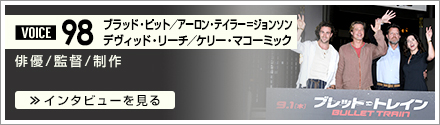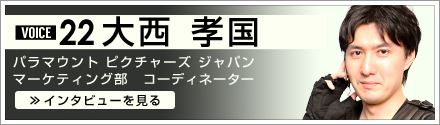―このほど『ヘヴンズ ストーリー』がファン待望の初のパッケージ化を迎えましたが、現在の率直な心境はいかがですか?
公開当時、映画館でしか上映しないことは作品の売りでもあったわけで、映画館での上映にこだわったということはあったのですが、それがここ最近になると配信の時代になった。ブルーレイやDVDがなくなるのでは? と言われているくらい売れていない。その売れていない配信中心の時代に円盤で所有する、ブツとして自分で持っていることにも意義があるのではと思うようになり、発売にいたったということはあります。
―映画館上映では、フィルムでの上映にこだわってもいましたよね。
『ヘヴンズ ストーリー』はフィルムで上映をしてきましたが、公開当時はぎりぎりフィルム上映だったんですね。その後、映画の上映システムはDCP、DLP上映といって、映画をデータ化して上映するのが一般的になりました。それはもう、目には見えない世界です。フィルムからDCP上映の流れと、DVDから配信上映への時代の変わり方は、そこにズレはあるけれども似ていると思うんです。それぞれブツだったものが、ブツというカタチがなくなっていく世の中なんですよね。
―この10年間だけを切り取ってみても、作品を取り巻く環境は激変しましたよね。
フィルムには、フィルムの良さがありました。劣化して味わいが深くなって、そのなかで蓄積していく映画館での記憶というものが宿って、年月を感じましたよね。DCP上映では、そういうものがなくなって、すべてが画一化されていった。すべて、同じような感じになっていく。そういうことよりも、映画というものはもっと自由で、選択肢があったほうがいい。選ぶ選択肢が豊富であれば、豊富であるほどいい。そういう意味では最後の抵抗じゃないけれど、DVDを出しましょうと。

―監督は、もともと山崎ハコさんのファンだったそうですね。監督として山崎さんを演出する立場としてかかわっていかがでしたか?
中学、高校からのファンでした。ハコさんは少しですが舞台経験はあるんですね。それで撮影当初は、少し芝居が大きかったんです。だから、「あまり表現したいとか考えないでください。思うだけでいいので」と言いました。それから繊細なニュアンスを出していただけるようになったと思います。アルツハイマーの病状もひどくなり、彼女の死の間際のシーンでは、岩手の廃墟の屋上でただ、ぼーっと座っているだけでしたが、どことなく想いがスクリーンに映っている気がするお芝居をしてくださって。それは本当にいい感じだなと思いました。
ハコさんって歌もそうですが、彼女の背中には風景が見えますね。幼い頃に育った大分県の田舎の風景かもしれないし、高校生の時に都会に出てきた横浜の風景かもしれないけれど、背中に風景を感じる人なんです。演じている最中もバックに風景を感じられるし、その画が見えてくるので、そういう意味では強い俳優にして表現者です。女優として、これは素晴らしいこと。決して演技ではない、本人が持っているキャラクターの強さというのか、その人の持っている芯の部分、それが出ていると思いました。
―緊張はしましたか(笑)?
不安は、どこかにあったのは確かです。自分でお願いしたはいいが、実物を見たこともなかったので(笑)。なので、正式にお願いする前に、彼女の舞台を観に行く機会がありまして。下北沢の駅前の小さな劇場でしたが、そこでは袖で歌っていて、お芝居はやっていなかったんです。でも、歌っている感じがよかったんですね。それで即お電話をさしあげて、青山のカフェかどこかでお会いして。脚本をお渡ししてお願いしました。
ただ、それから出演交渉をして、実はクランクインが一年後に。「準備不足で一年待ってほしい」と。だからハコさんは一年間脚本を持って準備していたわけです、これは大変なことだと思いました。寉岡萌希さんに至っては、最初お会いしてサトでお願いしたのが中学二年生、撮影は彼女が高二の時。大人になるギリギリの年齢だったんですね、それで無理矢理クランクインした事情もあります(笑)。

―『ヘヴンズ ストーリー』のような撮り方で、今後映画で追いかけたいテーマは何でしょうか?
展望はありますが、テーマは違うほうがいいですね。撮り方とテーマが同じだと似ちゃう気がするので、方法は同じだけれど内容は違うほうがいい気がしますけれどね。だから、自分のスタンスを変えないといけないと思うんですよ。この時は当事者でありたいとか渦中に入って撮りたいと思っていましたが、いまこういう方法論で同じような題材を描けるかっていうと、そんな気が実はしていないんです。僕らが取り組んだ時代とはもう違うので、スタンスを変えないといけない。
いまはコンプライアンス的なものがどんどんひどくなってきているというか、個人と加害者が面と向かってどうなるかという方法論が皆に響くかというと、違うような気がします。僕らが2000年代の終わりに撮影した雰囲気とはいまは違うので、『ヘヴンズ ストーリー』を作った方法で撮っていいかっていうと、ちょっと違うような気がするんです。だから、違う方法を模索したほうがいいとは思いますけどね。
―『ヘヴンズ ストーリー』を初めて観る人には、どうアピールをいたしますか?
復讐劇で売っていますが、タイトルは柔らかい感じで、それは僕らが作る時に大切にしていたイメージでもあるんです。子どもたちが重要な役柄でたくさん出てきますが、これは事件を経ての、ある意味彼らの成長譚でもあると思うんです。成長する姿を描いていると思う。あの子どもたちが成長するってことは、人の死の意味を知るということでもある。人間はいつか死にます。死の持っている厳しいことを知りますが、でも死があるからこそ人生は輝かしいということもある。そういうことを知る、子どもたちの成長譚でもあるわけですね。